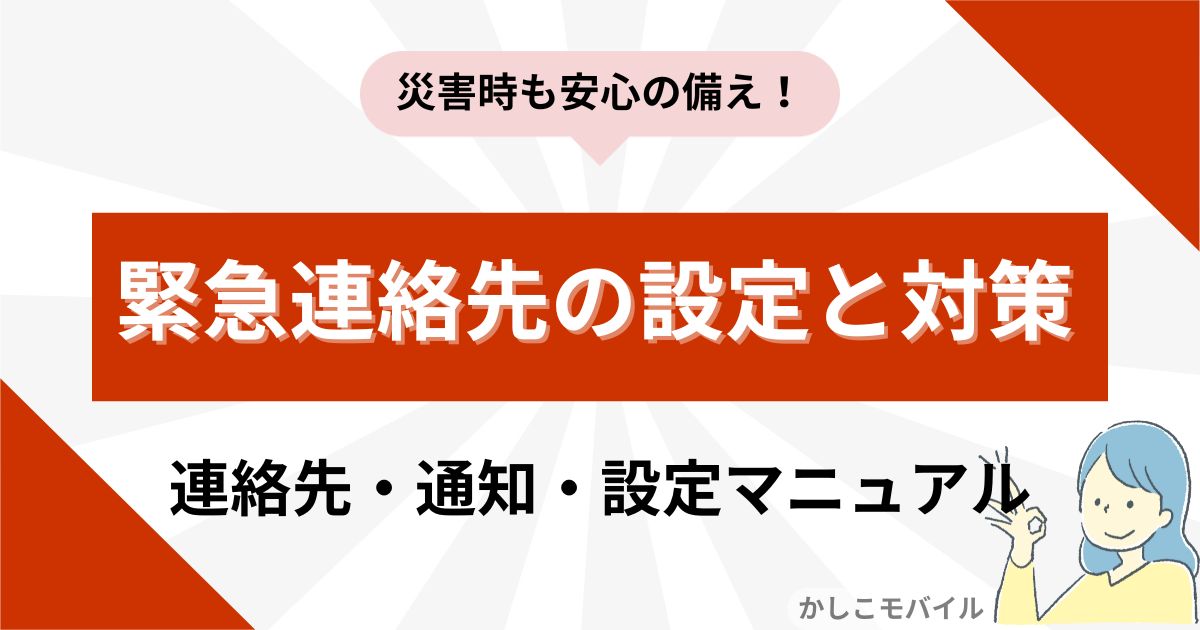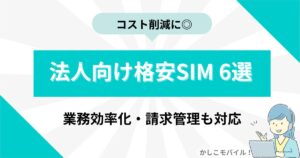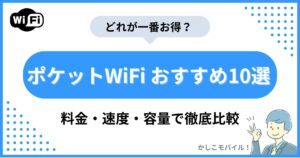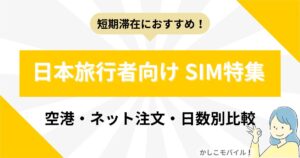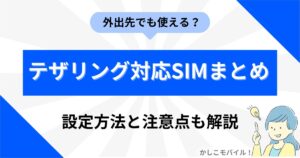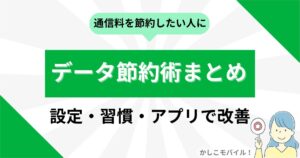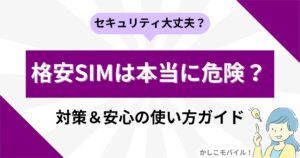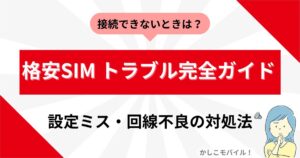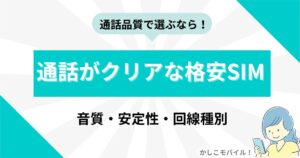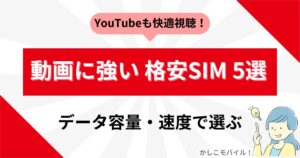スマートフォンの利用が当たり前となった今、災害や急病など“もしもの時”に備えておくことは、誰にとっても必要不可欠です。特に格安SIMを利用しているユーザーにとっては、「本当に緊急通報ができるのか?」「災害時にもちゃんと通信できるのか?」といった不安を感じることもあるでしょう。
本記事では、2025年最新の情報をもとに、格安SIMでも可能な緊急連絡先の設定方法や、緊急通報の可否、防災アプリの活用方法などを丁寧に解説します。iPhoneとAndroid、それぞれの設定手順や注意点も網羅しているので、初めての方でも安心して読み進められる内容となっています。
いざという時に後悔しないよう、この記事を参考に、今すぐ対策を始めましょう。
第1章:格安SIMでも緊急通報は可能?
格安SIMを利用している人の中には、「110番や119番などの緊急通報ってちゃんと使えるの?」と不安に思っている方も少なくありません。ここでは、格安SIMでの緊急通報の可否について、SIMの種類ごとに詳しく解説します。
音声通話対応SIMとデータ通信専用SIMの違い
まず、格安SIMには大きく分けて「音声通話対応SIM」と「データ通信専用SIM」があります。この違いによって、緊急通報の可否も変わってきます。
| SIMの種類 | 緊急通報(110番・119番など) | 通話機能 | 対応端末に依存 |
|---|---|---|---|
| 音声通話対応SIM | 可能 | あり | 一部端末で制限あり |
| データ通信専用SIM | 不可 | なし | IP電話で代替可否は要確認 |
音声通話対応SIM(通話SIM)は、一般的なキャリアのスマホと同様に、110番や119番といった緊急通報が可能です。これは通話機能が電話回線(音声回線)を使っているためで、緊急時でも問題なく利用できます。
一方で、データ通信専用SIMの場合、そもそも音声通話の機能自体がないため、電話番号を使った緊急通報はできません。このタイプのSIMを利用している場合は、代替手段の準備が不可欠です。
緊急通報ができない場合の対策
データ通信専用SIMや、IP電話を使っている場合は、以下のような対策を考えておく必要があります。
- 家族のスマホに緊急通報を任せる
- 公衆電話の位置を確認しておく
- 緊急時に備えてモバイルWi-Fiや音声通話付き予備端末を準備
- LINEやSNSなど、緊急時の連絡手段を共有しておく
特にIP電話(050から始まる番号など)では、緊急通報やフリーダイヤルへの発信が制限されていることが多く、緊急時には非常に不便です。通信専用SIMを利用している方は、防災の一環として「緊急時の通信手段マニュアル」を自分なりに用意しておくと安心です。
このように、格安SIMでも音声通話機能があれば緊急通報は可能です。しかし、利用しているSIMの種類によっては対応できないケースもあるため、自分の契約内容をしっかり確認し、備えをしておくことが重要です。
第2章:スマートフォンでの緊急連絡先の設定方法
災害や事故といった緊急時に、周囲の人がすぐに家族や医療機関へ連絡できるよう、「緊急連絡先」をスマートフォンに事前登録しておくことが非常に重要です。この章では、iPhoneとAndroid、それぞれの端末での設定方法と注意点を詳しく解説します。
iPhoneでの緊急連絡先の設定手順
iPhoneには、Apple純正の「ヘルスケア」アプリを使って、緊急連絡先や医療情報を設定する機能があります。以下の手順で簡単に設定できます。
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| 1 | ヘルスケアアプリを開く(iOSに標準搭載) |
| 2 | 右上のプロフィール写真をタップし、「メディカルID」を選択 |
| 3 | 「編集」をタップ |
| 4 | 緊急連絡先(家族や友人など)を追加、必要なら医療情報も入力 |
| 5 | 「ロック中に表示」をオンにする |
| 6 | 右上の「完了」をタップして保存 |
この設定をしておくと、スマホがロックされた状態でも、ロック画面から「緊急」→「メディカルID」を選ぶことで、誰でも設定された緊急連絡先にアクセスできます。
特に一人暮らしの方や高齢者の方は、この設定をしておくことで、いざという時に周囲の人が迅速に対応できるようになります。
Androidでの緊急連絡先の設定手順
Androidスマートフォンでは、端末やOSのバージョンによって設定方法が若干異なりますが、多くの機種で以下のような手順が使えます。
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 設定アプリを開く |
| 2 | 「安全と緊急」または「ユーザー情報」などの項目を探す |
| 3 | 「緊急情報」または「医療情報と連絡先」をタップ |
| 4 | 緊急連絡先や既往歴、アレルギー情報などを入力 |
| 5 | 表示方法を「ロック画面でも表示」に設定 |
| 6 | 保存をタップして完了 |
一部のAndroid端末では、「緊急情報」アプリがプリインストールされており、そこから直接登録ができるようになっています。
また、Googleアカウントに紐づけて緊急情報を保存できる機能もあり、端末が変わっても設定を引き継げるのが便利です。
設定時の注意点とアドバイス
緊急連絡先を登録する際は、以下のポイントを押さえておきましょう。
- 連絡が確実に取れる人を選ぶこと(複数登録が理想)
- 名前や続柄、連絡手段(電話番号・メール)を明確にする
- 定期的に情報の見直しを行う
- 医療情報(血液型、アレルギー、服薬情報など)も入力しておくと安心
特に高齢の家族をお持ちの方や、健康に不安のある方は、医療従事者が素早く適切な処置を取れるよう、医療情報の入力もおすすめします。
第3章:緊急速報メールと防災アプリの活用
格安SIMを使っていると、「緊急速報メール(エリアメール・Jアラートなど)は受信できるの?」と心配になる方も多いでしょう。また、災害時に備えて防災アプリを活用することも大切です。この章では、それぞれの対応状況や設定方法、おすすめのアプリについて詳しく解説します。
緊急速報メールは格安SIMで受信できる?
結論から言うと、緊急速報メールを受信できるかどうかは「SIMの種類」ではなく、「スマートフォン端末の対応状況」によって決まります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 受信可能かどうかの判断基準 | 使用端末が緊急速報(ETWS)に対応しているか |
| 格安SIMでの制限 | 原則なし(対応端末なら受信可能) |
| 確認方法 | 端末の「設定」→「通知」→「緊急速報メール」項目を確認 |
| 対応端末の例 | Pixelシリーズ、AQUOS、Galaxyの一部など |
| 非対応端末の例 | 一部中華系スマホ(例:UMIDIGI、OUKITELなど) |
端末によってはデフォルトで緊急速報通知がオフになっていることもあるため、必ず設定を確認しておきましょう。
おすすめの防災アプリ3選(2025年版)
緊急速報メールに加え、防災アプリを活用することで、災害時の情報収集能力が格段に高まります。ここでは、2025年時点で信頼性の高いおすすめアプリを紹介します。
| アプリ名 | 特徴 | 対応OS | 提供元 |
|---|---|---|---|
| Yahoo!防災速報 | 地震・津波・台風・避難情報などをリアルタイム通知 | iOS/Android | Yahoo! JAPAN |
| NHKニュース・防災 | ライブニュース+緊急速報、地域ごとの情報が強み | iOS/Android | NHK |
| 特務機関NERV防災 | 地震速報・気象情報・Jアラートを秒単位で通知 | iOS/Android | ゲヒルン株式会社 |
これらのアプリは、GPS情報をもとに地域ごとの通知を出してくれるため、格安SIMでも問題なく使用できます。通知音や通知方法もカスタマイズできるため、自分に合った使い方が可能です。
アプリ導入時のポイント
- 通知設定をオンにしておくこと
- 位置情報の利用を「常時許可」にすることで精度アップ
- 家族にも同じアプリを入れておくと連携がスムーズ
- 電池の最適化対象外に設定して通知遅延を防ぐ
災害はいつ発生するかわかりません。格安SIMを利用していても、これらのアプリをしっかり導入しておくことで、万が一の時に必要な情報をいち早く受け取ることができます。
第4章:災害時の通信手段と安否確認サービス
大規模災害が発生すると、携帯電話やインターネットの回線に大きな負荷がかかり、通常の通話や通信が困難になることがあります。そんなときに役立つのが、安否確認サービスや代替通信手段です。この章では、災害時に使える代表的なサービスや、格安SIM利用者が意識しておきたいポイントを解説します。
災害用伝言板・安否確認サービスとは?
災害発生時、通信規制が行われても最低限の連絡を取り合う手段として活用されるのが、災害用伝言板などの安否確認サービスです。
| サービス名 | 概要 | 格安SIM対応 | 利用方法 |
|---|---|---|---|
| 災害用伝言板(web171) | NTTが提供するWeb上の伝言板サービス | ○(誰でも利用可) | 災害用伝言板(web171) にアクセスし、電話番号でメッセージ確認・登録 |
| Google パーソンファインダー | Googleが提供する災害時安否確認データベース | ○ | Google パーソンファインダー (安否情報) にアクセスし、名前で検索・登録可能 |
| LINEの安否確認 | LINE公式アカウントから災害情報と安否確認が届く | ○ | アカウントを友だち追加し、指示に従って安否を登録 |
これらのサービスは、音声通話が使えない状況でも最低限の情報共有が可能になるため、災害時の連絡手段として非常に有効です。
SNSやメッセージアプリの活用
災害時、音声通話よりもデータ通信のほうがつながりやすい傾向があります。そのため、LINEやTwitter(現X)、Instagramなど、SNSやメッセージアプリを利用した安否確認も重要です。
おすすめの使い方:
- 家族や友人と、使うSNSアプリと連絡方法を事前に取り決めておく
- グループチャットを活用して、複数人の安否を一括で確認
- 「通話」よりも「テキストメッセージ(チャット)」を優先
また、LINEやFacebook Messengerなどのチャットアプリは、通話よりも通信容量が少なく、電波が弱い環境でも比較的使いやすいため、防災の観点からも非常に頼りになります。
通信が使えないときの備えも忘れずに
電波が完全に遮断された場合や、端末が使えない状況に備えて、以下のようなアナログな手段も準備しておくと安心です。
- 災害用伝言ダイヤル(171)の利用方法をメモしておく
- 家族で「集合場所」「連絡が取れないときの行動」を話し合っておく
- 必要な連絡先は紙に書いて財布などに入れておく
災害時に必要なのは「複数の連絡手段の確保」と「事前の取り決め」です。格安SIMでも、適切に準備しておけば十分に対応が可能です。
第5章:格安SIMユーザーが知っておくべき注意点
格安SIMはコストパフォーマンスが高く、多くの人に支持されていますが、緊急時や災害時には特有の制限や注意点が存在します。この章では、格安SIMユーザーが特に注意すべきポイントを最新の情報に基づいて解説します。
IP電話アプリでは緊急通報ができないことがある
多くの格安SIMユーザーが050番号のIP電話アプリ(例:SMARTalk、050 plusなど)を利用していますが、これらのアプリでは緊急通報(110番・119番など)ができないケースがほとんどです。
| 通話手段 | 緊急通報対応 | 備考 |
|---|---|---|
| 音声通話SIM(090/080番号) | ○ | 通常の携帯電話と同様に利用可 |
| IP電話(050番号) | × | 緊急通報やフリーダイヤルに非対応のものが多い |
| データ通信SIM+通話アプリ | × | アプリによって通報不可、または回線が不安定な場合あり |
IP電話をメインに使っている人は、いざという時に緊急通報ができないリスクを理解し、家族や同居者などに音声通話可能な端末を備えてもらうか、予備の通話SIMを準備するなどの対策が求められます。
災害時の通信制限と優先順位について
災害発生時、携帯各社では通話やデータ通信に制限をかける場合があります。これは回線のパンクを防ぎ、重要な通信を優先させるために行われる措置です。
| 通信制限の対象 | 優先される通信 | 制限の可能性が高い通信 |
|---|---|---|
| 格安SIM(MVNO) | 緊急通報・災害伝言板 | 通常通話・動画閲覧などの高容量通信 |
| 大手キャリア回線 | 緊急機関・公的通信 | 一般ユーザーのトラフィックは一部制限の可能性 |
格安SIMは大手キャリアの通信網を間借りしているため、混雑時には通信速度や優先度が低くなる傾向があります。特に災害時は、以下のような対策が有効です。
- データ容量を節約するモードに切り替える
- 軽量版アプリ(LINE Liteなど)を活用する
- 通信が安定する時間帯を見極めて連絡する
- 予備のWi-Fi接続手段(モバイルルーター、テザリングなど)を用意しておく
通信制限下でも最低限の連絡ができるよう、日頃から複数の通信手段を用意しておくことが大切です。
サポート体制の違いにも要注意
大手キャリアと比べ、格安SIMはサポート体制が限られている場合が多く、トラブル発生時にすぐに相談できないこともあります。災害時は特にカスタマーサポート窓口も混雑しやすいため、以下のような備えをしておきましょう。
- 緊急時の対応マニュアルをダウンロード・印刷しておく
- 利用中の格安SIM会社の緊急対応方針を事前に確認する
- 端末の設定変更やアプリの使い方を普段から練習しておく
備えがあるかないかで、緊急時の安心感は大きく変わります。
おわりに
格安SIMを利用していても、緊急通報や災害時の安否確認は、しっかりと準備しておくことで十分に対応が可能です。今回ご紹介したように、スマートフォンの緊急連絡先設定、緊急速報の受信設定、防災アプリの導入、災害用伝言板の活用など、事前にできる対策は数多くあります。
特に格安SIMは、利用環境によって緊急時の通信制限を受けやすかったり、サポートが弱かったりといった特性がありますが、それらを理解し、適切に備えることで不安は大きく軽減されます。
いざという時に慌てないためにも、今日からできることから始めましょう。そして、大切な家族や友人とも一緒に設定や情報の共有をしておくことで、安心と安全を広げていけます。
この記事が、あなたとあなたの大切な人たちを守るための一助となれば幸いです。